- 36協定の記入上の注意点
- 36協定の実際の記入例ご紹介
36協定の実際の記入例のご紹介
36協定の書き方をご紹介します。
①36協定届における押印・署名の廃止
(協定書を兼ねる場合は、署名、または記名・押印が必要)
②36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設
記載すべき項目は旧様式同様、以下の通りです。
- 事業の名称
- 時間外、休日労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 延長することができる時間
- 1日を超える一定の期間(起算日)、期間
- 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者
- 所定休日
- 労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻
- 協定の成立年月日
- 協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職氏名
- 職、氏名
- 協定の当事者の選出方法
- 使用者職氏名
- 延長することができる時間
36協定届(一般条項)
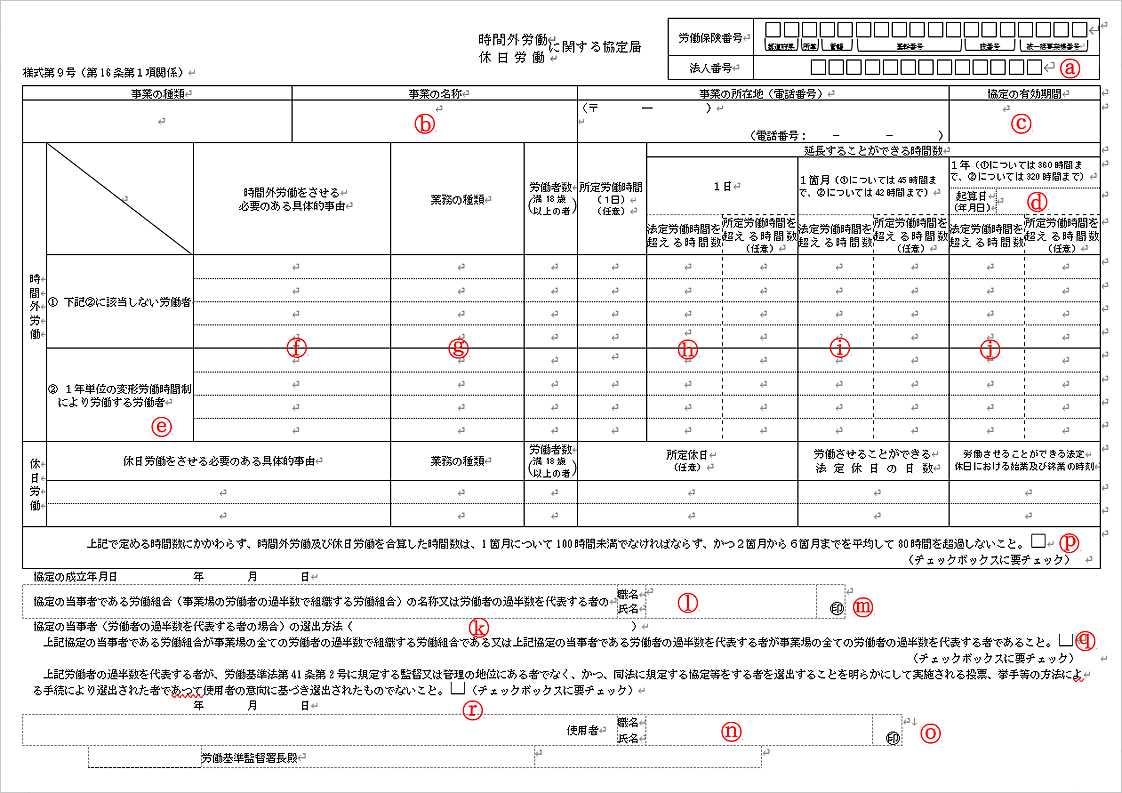
- 労働保険番号・法人番号を記載します。
- 事業場(工場、支店、営業所 等)ごとに協定を結びます。
- この協定が有効となる期間を定めます(1年間とすることが望ましい)。
- 1年間の上限時間を計算する際の起算日を記載します。その1年間においては協定の有効期間にかかわらず、起算日は同一の日である必要があります。
- 対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制が適用される労働者については、②の欄に記載します。
- 事由を具体的に記載します。
- 業務の範囲を細分化し、 明確に定めます。
- 1日の法定労働時間を超える時間数を定めます。
- 1カ月の法定労働時間を超える時間数を定めます。①は45時間以内、②は42時間以内です。
- 1年の法定労働時間を超える時間数を定めます。①は360時間以内、②は320時間以内です。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、36協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・挙手などの方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載します。使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません
- 労働者代表の職名氏名を記載します。(管理監督者は労働者代表にはなれません)
-
別途協定書を締結する場合は、署名・押印が不要となります。(記名は必要です)
協定書と協定届を兼ねる場合は、署名、または記名・押印が必要です。 - 代表者を記載します。
-
別途協定書を締結する場合は、署名・押印が不要となります。(記名は必要です)
協定書と協定届を兼ねる場合は、署名、または記名・押印が必要です。 - 時間外労働と法定休日労働を合計した時間数は、月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内でなければいけません。これを労使で確認の上、必ずチェックを入れます。チェックボックスにチェックがない場合には、有効な協定届とはなりません。
- チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要件に適合している協定届とはなりません。
- 使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。 チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要件に適合している協定届とはなりません。
36協定届(特別条項)
特別条項付きの36協定届は様式が2枚にわたり、「限度時間内の時間外労働についての届出書」と「限度時間を超える時間外労働についての届出書」を届け出る必要があります。
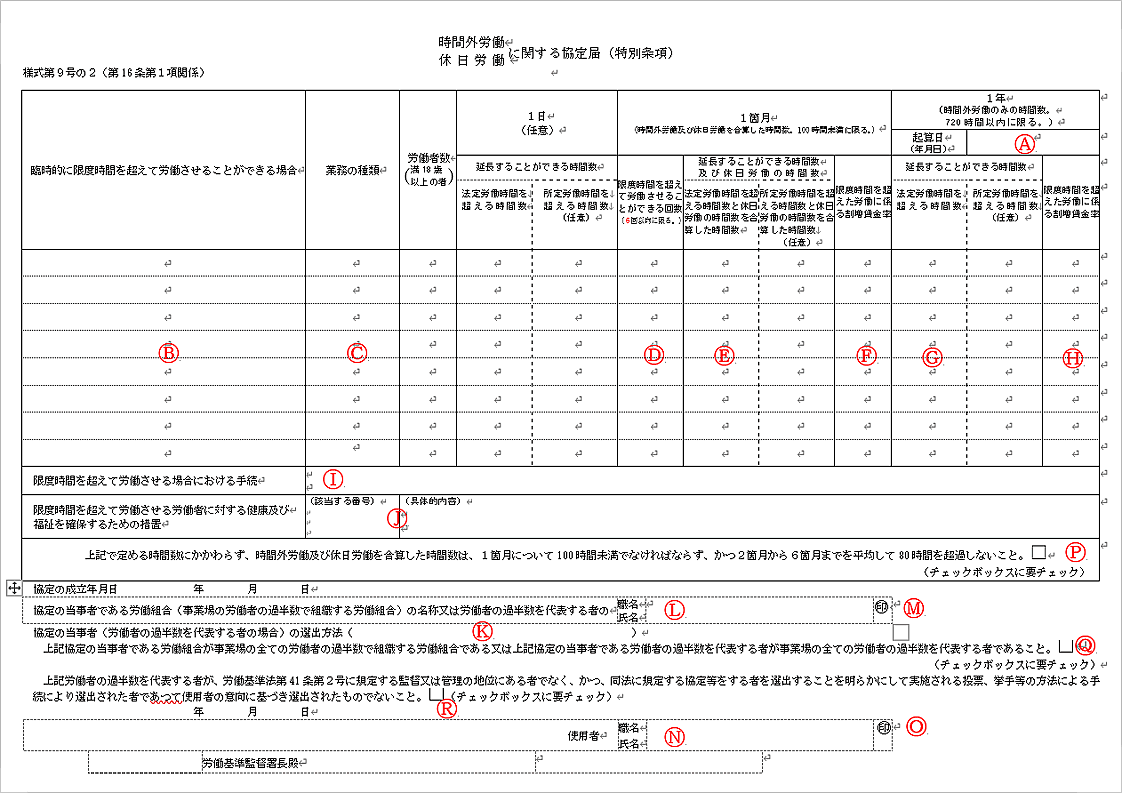
- 1年間の上限時間を計算する際の起算日を記載します。その1年間においては協定の有効期間にかかわらず、起算日は同一の日である必要があります。
- 事由は一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものに限り、できる限り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
- 業務の範囲を細分化し、明確に定めます。
- 月の時間外労働の限度時間(月45時間または42時間)を超えて労働させる回数を定めます(年6回以内に限る)。
- 限度時間(月45時間または42時間)を超えて労働させる場合の、1カ月の時間外労働と休日労働の合計の時間数を定めます(月100時間未満に限る)。なお、この時間数を満たしていても、2~6カ月平均で月80時間を超えてはいけません。
- 限度時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金率を定めます。この場合、法定の割増率(25%)を超える割増率となるよう努めてください。
- 限度時間(年360時間または320時間)を超えて労働させる1年の時間外労働(休日労働は含まない)の時間数を定めます。年720時間以内に限ります。
- 限度時間を超えて時間外労働をさせる場合の割増賃金率を定めます。この場合、法定の割増率(25%)を超える割増率となるよう努めてください。
- 限度時間を超えて労働させる場合にとる手続きについて定めます。
- 限度時間を超えた労働者に対し、裏面の記載心得 1(9)①~⑩ の健康確保措置のいずれかの措置を講ずることを定めます。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、36協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・挙手などの方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載します。使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません
- 管理監督者は労働者代表にはなれません。
-
別途協定書を締結する場合は、署名・押印が不要となります。(記名は必要です)
協定書と協定届を兼ねる場合は、署名、または記名・押印が必要です。 - 代表者を記載します。
-
別途協定書を締結する場合は、署名・押印が不要となります。(記名は必要です)
協定書と協定届を兼ねる場合は、署名、または記名・押印が必要です。 - 時間外労働と法定休日労働を合計した時間数は、月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内でなければいけません。これを労使で確認の上、必ずチェックを入れます。チェックボックスにチェックがない場合には、有効な協定届とはなりません。
- チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要件に適合している協定届とはなりません。
- 使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。 チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要件に適合している協定届とはなりません。